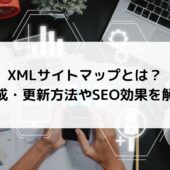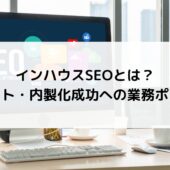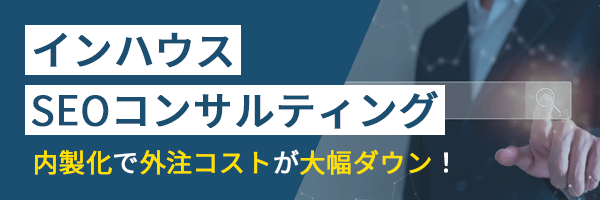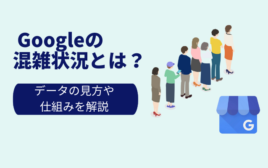- 2026.1.26
- SEO
重複コンテンツとは?SEOにどんな影響があるのか解説

Webサイトを運営していると
「重複コンテンツってSEOに悪いって聞くけど、正直よく分からない」
と感じたことはありませんか?
結論から言うと、重複コンテンツが存在すると、多くの場合「Googleなどの検索エンジンからの評価が分散してしまう」ことが問題になります。この場合は、意識していない内部構造やタグ設定の影響によって起こることもあります。
そこでこの記事では、
- 重複コンテンツとは何か
- なぜSEOに悪影響が出るのか
- よくあるNG例
- 重複コンテンツを簡単に確認する方法
- 今日からできる簡単な対策方法
をくわしく解説します。
結果が違う本格SEO運用代行なら
フリースクエアにお任せください!
プロのSEO運用代行を低コストで実現!
目次
重複コンテンツとは?

重複コンテンツとは、WEBサイト上で
ほぼ同じ、またはとても似た内容のページが複数のURLで存在している状態
を指します。
ポイントは「完全に同じでなくても重複とみなされる」という点です。
一部を言い換えていても、伝えている主旨や価値がほぼ同じであれば、重複コンテンツになる場合があります。
もう少しわかりやすく説明すると、
Googleは、
「この検索キーワードに対して、どれが一番役立つか?」
を判断して、検索結果に表示するものを選んでいます。
しかし、Webサイト上で同じようなコンテンツがいくつもあると、
- どれが一番大事なのか分からない
- 評価をどのページに集めればいいのか決められない
という状態になります。
これが、重複コンテンツがSEOで問題になる理由です。
初心者でもイメージしやすい例
次のようなケースは、重複コンテンツになりやすい典型例です。
- 同じコンテンツをコピーして、複数のページに掲載している
- タイトルだけ変えて、コンテンツがほぼ同じ記事を何本も書いている
- 「地域名+サービス名」のページを量産し、本文がほぼ同一
- 商品ページごとに、同じ文章をそのまま使っている場合
これらはすべて「URLは違うけど、中身はほとんど同じ」状態です。
「内部」と「外部」があるが、まずは内部だけ意識すればOK
重複コンテンツには大きく分けて2種類あります。
内部重複:自分のサイト内でコンテンツがかぶっている
外部重複:他サイトとコンテンツがかぶっている
ただし、まず気にすべきなのは「内部重複」だけで十分です。 多くの場合、SEOに影響が出るのは「自分のサイト内で似たものを作りすぎているケース」だからです。
特に、
- 同じテーマの記事を別URLで公開
- タグページやカテゴリページの自動生成設定
- CMSの仕様で似た一覧ページが量産される場合
など内部のタグ設計・記事構成の重複によるものが多いです。
なぜ重複コンテンツはSEOに悪影響なのか?

重複コンテンツがあると、SEOにどのような悪影響を与えるのか、くわしく解説します。
①Googleが評価すべきページを選べなくなる
Googleは、検索結果に表示するページを決めるとき、 「この検索キーワードに対して、一番役立つものはどれか?」 を常に判断しています。
しかし、Webサイト上でほぼ同じコンテンツが複数あると、
- Aも同じことを書いている
- Bもほぼ同じ
- どちらを代表として評価すべきか決めきれない
という状態になります。
その結果、SEO評価が1ページに集まらず、複数ページに分散してしまいます。
本来なら「評価10」をもらえるはずなのに「5+5」や「3+3+4」に分かれてしまうイメージです。
②検索順位が上がりにくくなる
SEOでは、評価が集まっているものほど検索順位が上がりやすい仕組みになっています。
しかし、Webサイト上で重複コンテンツやタグの乱立があると、
- どれも中途半端な評価になる
- 「あと一歩」で上位に届かない
- 順位が安定しない
といった状態になりやすくなります。
特によくあるのが「ちゃんと記事を書いているのに、なぜか順位が上がらない」という場合です。その原因が「似たページを作りすぎていることだった」ということも少なくありません。
③インデックスがうまく整理されなくなる
Googleは、ページを見つけ、主旨を理解し、検索結果に登録(インデックス)します。
Webサイト上で重複コンテンツが多いと、
- どれを登録すべきか迷う
- 古いページや意図しないものが選ばれる
- 大事なページが後回しになる
といったことが起こります。
その結果、
- 表示させたいページが検索結果に出ない
- 更新したコンテンツがなかなか反映されない
など、不安定な状態になります。
④ユーザー体験も悪くなり、間接的にSEOに影響する
重複コンテンツは、ユーザーにも分かりにくさを与えます。
たとえば、
- 検索結果に似たものがいくつも並ぶ
- どれを見れば答えがあるのか分からない
- 何ページも行き来しないと情報が揃わない
こうした体験は、
- すぐに戻る(離脱)
- 長く読まれない
といった行動につながりやすくなります。
Googleは「ユーザーにとって役立つかどうか」を重視しているため、間接的にSEO評価にも影響が出やすくなります。
特に注意すべき重複コンテンツの例

ここでは、やってしまいがちな重複コンテンツの例をご紹介します。
それぞれ、なぜ問題なのかと抑えるべきポイントをまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
①URLは違うが、中身がほぼ同じ
一番多いのがこのケースです。
よくある例
https://example.com
https://www.example.com
https://example.com/
http://example.com
このように「wwwあり/なし」「末尾スラッシュあり/なし」「httpとhttps」といったURLの見た目に違いがあっても、表示される内容が同じであれば重複コンテンツになります。
なぜ問題なのか?これも、Googleから見ると「同じページが複数あるサイト」に見えてしまい、どのURLを評価すればいいか迷う状態になります。特に正規URLの設定やrel=“canonical”のタグ指定が曖昧な場合は影響が大きくなります。
対策方法「URLは1ページにつき1つ」という意識を持つだけで十分です。正規URLの設定や、必要に応じたタグの指定も合わせて確認しましょう。
②似た内容の記事を何本も書いてしまっている
Webサイトを運営していると、「SEO対策のために記事を増やそう」と思った結果、中身がかぶった記事を量産してしまうケースも非常に多いです。
よくある例
「重複コンテンツとは?」の記事が複数ある
タイトルは違うが、結論や説明がほぼ同じ
過去記事と新記事で言っていることが変わらない
Googleは「どの記事を検索結果に出せばいいの?」と判断できなくなり、どれも中途半端な評価になってしまいます。
対策方法同じテーマの記事は「1番わかりやすい1本」にまとめた方がSEO的に有利です。必要な場合は、内部リンクやタグ整理、記事統合の設定も行いましょう。
③地域名・サービス名だけ変えて本文を使い回している
Webサイトの中でも、地域ページやサービスコンテンツで特に多いパターンです。
よくある例
「東京の〇〇」
「大阪の〇〇」
「名古屋の〇〇」
ほとんどが同じで、地名だけが違うものを大量に作っているケースです。
Googleから見ると「名前を変えただけで、中身は同じ」と判断されやすく、評価が分散してしまいます。
対策方法地域ページを作る場合は「その地域ならではの情報があるか?」を意識することが重要です。独自データ・事例・サポート内容を加える設定にしていきましょう。
④商品説明・サービス説明をそのまま使い回している
ECサイトやサービスサイトで非常に多い例です。
よくある例
すべての商品ページで同じ
メーカー提供の説明文をそのまま掲載
紹介文を全ページでコピー
同じようなものが増えると、Googleは価値の違いを見出せません。
その結果、
- どの商品ページも評価されにくい
- 検索結果に表示されにくい
といった状態になります。
対策方法少しでも「特徴」「使い方」「選ばれる理由」などを足すだけでも改善につながります。構造化データのタグ設定や内容差別化の設定も検討しましょう。
⑤カテゴリページ・一覧ページが増えすぎている
ブログやメディア運営で起きやすいケースです。
よくある例
カテゴリページとタグページがほぼ同じ
タグ一覧・記事一覧ページが大量にある
中身のない一覧ページが増えている
一覧ページばかり増えると、
- 中身のあるコンテンツが埋もれる
- Webサイト上でどれが重要か分かりにくくなる
となります。
対策方法「このページは検索結果に出したいか?」を基準に考えると判断しやすくなります。
重複コンテンツを簡単に確認する方法

重複コンテンツは、専門ツールや難しい設定を使わなくても確認できます。
最初のうちは「全部やろう」とせず、次の2つの方法だけ押さえれば十分です。
方法①Google検索で文をそのまま調べる
まずは、最も簡単で手軽な対策方法です。
- 1.対象のページから、1〜2文ほど文をコピー
- 2.Google検索で、その文を「”文章”」のようにダブルクオーテーションで囲んで検索
- 3.検索結果を確認する
- 自分のサイト内で、同じ文のページが複数出てこないか
- 自分が作った覚えのないページが表示されていない場合
- 文の使い回しによる重複
- 同じコンテンツが複数あるかどうか
特に「地域ページ」「サービス説明」「商品説明」などは、この方法で見つかりやすい場合があります。
方法②Google Search Consoleでチェックする
次におすすめな方法が、Google公式ツールの「Google Search Console」です。
やり方- 1.Google Search Consoleで、対象サイトを選択する
- 2.左メニューの「インデックス作成」の「ページ」を選択する
- 3.「ページがインデックスに登録されなかった理由」を確認する
「重複しています」
「別のURLを正規ページとして選択しています」
といった表示が出ていないか確認しましょう。
Googleが「このページは重複している」と判断しているか
自分が意図していないURLが正規扱いされていないか
「重複があるかどうか」を把握できれば十分です。
重複コンテンツがあったら、どうするの?

サイトの重複コンテンツ対策で一番大事なのは「どれを残すか」ではなく「ページの役割をはっきりさせること」です。
そのため対策として、次の3ステップで考えてください。
対策① このページは何のためのページか
サイトの重複コンテンツ対策で、まずやるべきことは、
「これは、誰のどんな悩みを解決するためのページか?」
を言葉にすることです。
具体的には、2つを見比べながら、
- どんな人に向けて書いている?(初心者/経験者など)
- どんな疑問に答えている?
- このコンテンツを読んだ人は、何が分かる?
を整理していきましょう。
次のような場合は、役割がかぶっています。
- どちらも「重複コンテンツとは何か」を説明している
- 読み終わった後に得られる知識がほぼ同じ
- タイトルは違うが、構成と結論が同じ
これらが「どっちを読んでも同じ」なら、役割は同じです。
対策② 本当に2ページ必要か
次の対策として考えるのは、「ユーザーの立場で見て、2ページ必要か?」です。
- 1ページだけ読めば満足できるか?
- わざわざ2ページ読む意味があるか?
を整理していきましょう。
もし、「1ページで十分だな」と感じたらその2ページは1つにまとめた方が良い可能性が高いです。
例えば、
A:重複コンテンツとは?
B:SEOにおける重複コンテンツの意味
この2つがほぼ同じなら、「重複コンテンツとは?」1ページに集約した方が分かりやすいです。
反対に、
A:初心者向け「重複コンテンツとは?」
B:実践者向け「重複コンテンツの直し方」
この2つは読む人・目的が違うため、それぞれの役割が分かれているので、2ページのままでOKです。
対策③残すなら、どちらを育てるか
「まとめる」「整理する」と決めたら、どちらを中心に育てるかを決めます。
次の中で、多く当てはまる方を残します。
- 説明が分かりやすい
- 情報が新しい
- 文章が整理されている
- 今後も更新していきたい
- 問い合わせや導線につながっている
すべて当てはまる必要はありません。「育てやすそう」な方でOKです。必要に応じて、内部リンクの設定やカテゴリ/タグの整理も行うと効果的です。
では、残さない方はどうするか。
次の考え方で十分です。
- 中身がかぶっている → 統合する
- ほとんど使っていない → 整理する
- 古い情報しかない → 更新して統合する
「残さない=失敗」ではありません。むしろ、サイトを強くするための前向きな対策方法です。
サイトの重複コンテンツ対策で一番大切なのは「Googleのため」より「ユーザーが迷わないか?」という視点です。
- このページは何のためにあるのか
- 他と役割がかぶっていないか
この2点を意識するだけで、重複コンテンツの問題は自然と減っていきます。
よくある質問

サイトの重複コンテンツについて調べていると、多くの方が同じところで不安になります。
ここでは、その「つまずきやすいポイント」をまとめて解消します。
Q. 重複コンテンツは、なぜSEOに悪影響なのですか?
答え:
ペナルティになるからではなく「評価が分散してしまうから」です。
Googleは「この検索キーワードに対して、どのページが一番役立つか」を決めて、検索結果に表示します。
しかし、
- 内容がほぼ同じ
- どちらも似たタイトル・似た文章
- 違いがほとんど分からない場合
が複数存在すると、Googleは
「どのページを評価すればいいんだろう?」
「AもBも似ているけど、どちらが本命?」
と迷ってしまいます。
その結果、
本来1ページに集まるはずの評価(SEO評価)が複数ページに分散する。
すると、どのページも「中途半端な評価」になる。
結果として、順位が上がりにくくなる/下がる。
という事態が起こります。
Q. 重複コンテンツは防げますか?
答え:
似たコンテンツを作りすぎない、使い回さない、といった意識だけでも十分に防げます。
特に意識すべきポイントは、次の3つです。
- 地域名だけを変えた
- 見出し構成がほぼ同じ
- 内容は同じで、言い回しだけ少し変えた
「このページは、他と何が違うのか?」を自分で説明できない場合、重複の可能性が高いです。
② コピペ・使い回しをしない- 過去の記事からの丸コピー
- 説明文をそのまま別ページに流用
これらは、非常にありがちな原因です。
同じことを伝える場合でも、
- 視点を変える
- 具体例を変える
- 読者(初心者/比較検討中など)を変える
このような対策をすることで「別ページとしての意味」を持たせることができます。
③ 「1テーマ=1ページ」を意識する「このテーマは、このページで完結させる」という考え方を持つだけで、重複はかなり防げます。特に、タグやカテゴリの自動生成設定により似た一覧ページが量産される場合は要注意です。
Q. 修正したらどれくらいで影響が出ますか?
答え:
すぐに変わる場合もあれば、数週間〜数ヶ月かかる場合もあります。ただし、放置するより確実に改善につながります。
ここで大事なのは、即効性を期待しすぎないことです。
Googleは、
- ページの変更を発見する(クロール)
- コンテンツを再評価する
- 他との関係性を整理する
- 検索結果に反映する
という段階を踏みます。
そのため、
- 軽微な修正 → 比較的早く反映されることもある
- 大きな構造変更 → 数週間〜数ヶ月かかることもある
という違いが出ます。
重複コンテンツは、放置しても自然に良くなることはほぼありません。むしろ、サイト全体の評価を下げ続ける可能性があるという性質があります。
一方で、重複を整理したり、タグの設定を見直したり、評価させたいページを明確化することで、本来評価されるべきページにSEO評価が集まりやすくなります。
成果にコミットするSEOコンサルティングなら
フリースクエアにお任せください!
豊富な実績とインハウス(内製化)支援も可能!
まとめ
重複コンテンツは、SEO対策の中でも「知らないうちにSEOの足を引っ張ってしまう」代表的な原因です。
もし今「記事をたくさん書いているのに成果が出ない」「SEOが難しく感じている」ということであれば、「増やす」よりも「整理する」ことを意識してみてください。
重複コンテンツを減らし、役割がはっきりしたページだけを残すことで、SEO対策は自然と良い方向に進んでいきます。
SEOで一番大切なのは「分かりやすさ」です。
重複コンテンツ対策は、難しいSEOテクニックではありません。
「このページは、何のためにあるのか?」
「他と役割がかぶっていないか?」
この2つを意識することが、結果的にSEO評価を高める一番の近道です。
WRITER

ライターMT
ライターMTの記事一覧複数メディアのSEO対策担当者を8年以上経験。SEO知識の他に、健康、脱毛、恋愛、コンプレックスなどのジャンルも得意。これまで500本以上のコンテンツ制作と上位表示実績を持つ。
キーワード選定からライティングまでを一貫して行うため検索意図を把握する能力が高い。
重複コンテンツとは?SEOにどんな影響があるのか解説
この記事が気に入ったら
いいね!しよう