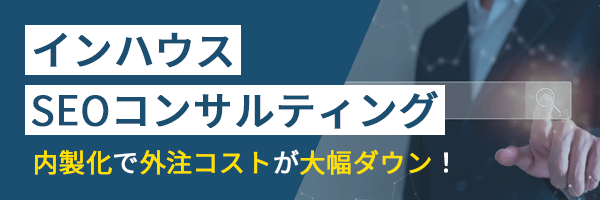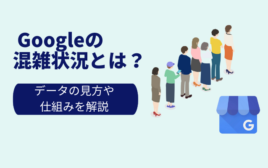- 2025.7.16
- SEO
構造化マークアップとは?SEOの効果や書き方をわかりやすく解説

構造化マークアップとは、ウェブページ内のコンテンツに対して『これは何の情報か』を示す追加の記述(構造化データによる意味付け)を施すことです。
具体的には、HTMLに特定のタグや属性、またはスクリプトを用いてデータの意味を構造化(マークアップ)することです。これにより検索エンジン(Googleなどのクローラー)がページ内容を正しく理解しやすくなり、検索結果における表示(リッチリザルトなど)に良い影響を与えることが期待できます。
このように検索エンジンにページ内容を正しく理解させるために構造化マークアップを活用することは、重要なSEO対策の1つです。
構造化マークアップの定義から種類(JSON-LD・RDFa・Microdata)やメリット、SEOへの影響、具体的なマークアップ方法、便利なツールの使い方(リッチリザルトテストやデータハイライター等)、さらにCMSと連携した実装方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。
ブログ記事などに構造化データを導入したいWebマーケティング初心者〜中級者の方は、ぜひ参考にしてくださいね。
結果が違う本格SEO運用代行なら
フリースクエアにお任せください!
プロのSEO運用代行を低コストで実現!
目次
構造化マークアップとは?(概要と定義)

先ほどもお伝えした通り、構造化マークアップとは、Webページ上のテキストやコンテンツに「これはどういう種類の情報か」という意味を持たせるマークアップ(記述)をすることです。
ページ上の文章を読めば「これは商品説明だな」「これはレシピの記事だな」と理解できますよね。でも、検索エンジンのクローラーは構造化されていなければその内容を正しく判断できません。
例えば、ページに「Apple」と書いてあっても、それが果物なのか企業名なのか、人名なのか、通常のHTMLだけでは検索エンジンが構造化されていない情報の意味を正確に判断することはできず、構造化マークアップの活用が求められます。つまり、コンテンツの意味が検索エンジンに伝わらないと、SEOの適切な評価を受けにくい可能性があります。
そこで活用されるのが構造化データによるマークアップです。
HTMLの要素に追加の情報(メタデータ)を記述(マークアップ)することで、「この単語(Apple)は企業名(Organization)である」や「この数字はレビューの星評価である」といった意味付けを機械に伝えることができます。これをページ内の適切な場所に埋め込むことで、検索エンジンはコンテンツをデータとして理解しやすくなります。
このように、構造化マークアップによってページ上のコンテンツに意味を持たせれば、検索エンジンに正しく情報が伝わり、SEOの観点からも有利になるのです。
通常のHTMLマークアップとの違い
通常のHTMLマークアップ(例えば<div>や<span>タグなど)は、ページの構造や見た目を整えるためのものです。これらのタグ自体には「意味」はなく、クローラーから見ると単なる容器や装飾に過ぎません。
構造化マークアップの場合はそれとは異なり、HTML内の単語やフレーズに「これは〇〇という種類のデータだ」という意味的なラベル付けを行います。
例えば、通常のHTMLでは <p>営業時間:9:00〜18:00</p> と書くだけでは構造化されていない情報として扱われてしまいますが、構造化マークアップを使えば「営業時間」という情報を示すタグ付け(例えばBusinessHoursという属性)を追加できます。その結果、検索エンジンはそのコンテンツが営業時間情報であると理解できるのです。
構造化マークアップを行うことは検索エンジンへの情報伝達を強化し、SEO対策としても有効だと言えます。
構造化データの種類と記述方法(シンタックス)

構造化データを実装する方法(シンタックスとも呼ばれます)には、主に次の3種類があります。
- Microdata(マイクロデータ)
- RDFa(アールディーエフエー)
- JSON-LD(ジェイソンエルディー)
それぞれ記述の仕方や適用できる範囲が異なります。主要な検索エンジンはいずれの形式もサポートしているため、SEO上はどの方式を用いても構造化データのマークアップ自体の効果は同じです。
では、それぞれの方式の特徴を解説します。
Microdata(マイクロデータ)
Microdataは、HTML5で導入された構造化データの記述方法です。主にHTMLの本文内(<body>要素内)で使用し、対象となるデータの近くに属性を追加する形でマークアップします。
例えば、<div>タグに対してアイテムスコープ(itemscope)やアイテムプロパティ(itemprop)といった属性を埋め込んでいくことで、「この部分のテキストは〇〇という意味です」と指定できます。
MicrodataはHTMLの要素内に直接書き込むため、ページごとに細かく実装できますが、その反面、コンテンツごとにHTMLコードを編集する手間がかかります。またHTML5に準拠したページでないと使えないという制約もあります。
RDFa(アールディーエフエー)
RDFa(Resource Description Framework in attributes)は、XHTMLやHTML5以外のXMLベースのドキュメントでも使える構造化データの記述方式です。Microdataと同様に、対象のデータ近くのタグに属性を書き込む点は似ています。
例えば<span>タグ内にpropertyやtypeofといった属性を追加し、その内容をマークアップします。RDFaは<body>要素内だけでなく<head>要素内にも記述でき、より柔軟にマークアップ可能です。
Microdataとの主な違いは使用できる環境の広さ(HTML5に限らず利用可)ですが、基本的な記述ルールは類似しており、こちらも対象ごとにHTMLを編集する必要があります。
JSON-LD(ジェイソンエルディー)
JSON-LD(JavaScript Object Notation for Linked Data)は、構造化データをJSON形式のスクリプトとして記述する方法です。HTMLの<script>タグ内にJSONオブジェクトとしてデータを記述します。
MicrodataやRDFaと異なり、マークアップする項目をその近くに書く必要はありません。ページのどこに記述しても良く(通常は<p>内にまとめて記述)、既存のHTML要素を修正しないのでサイトの見た目に影響を与えません。
Googleも公式にJSON-LDでのマークアップを推奨しており、現在もっとも一般的に使われている構造化データの実装方法です。「JSON-LDは、構造化データを扱う中で最も主流の手法であり、可読性が高く、サイト運営者や開発者にとってもメンテナンスしやすいというメリットがあります。そのためSEO業界においても事実上の標準となっています。
以上の3つのシンタックスにはそれぞれ特徴がありますが、Googleなど主要な検索エンジンはいずれの形式もサポートしています(※data-vocabulary.orgという古いボキャブラリーは現在サポート終了)。
結論として、特に理由がなければJSON-LD形式で構造化データを実装するのが無難でしょう。JSON-LDであれば既存のHTMLを壊す心配もなく、構造化データの導入支援ツールやCMS機能とも相性が良いです。
構造化データマークアップの具体例(記述サンプル)

それでは、構造化マークアップが実際にどのように記述されるか具体的なコード例を見てみましょう。ここではブログ記事のページを想定し、JSON-LD形式で記事の構造化データを記述する例を示します。
次のコードは、ブログ記事(BlogPosting)のタイトル・公開日・著者をマークアップしたJSON-LDのサンプルです。
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BlogPosting",
"headline": "記事タイトル",
"datePublished": "2025-04-01",
"author": {
"@type": "Person",
"name": "サイト管理人"
}
}
</script>
このように、<script type="application/ld+json">タグの中にJSON形式でデータを記述します。
ポイントとなる要素を見てみましょう。
使用するボキャブラリー(語彙体系)の指定です。基本的にschema.orgという大規模なボキャブラリーを利用します。
このデータの種類(タイプ)を指定しています。BlogPostingはブログ記事を表す構造化データのタイプです(より一般的な記事ならArticle、ニュース記事ならNewsArticleというタイプもあります)。
プロパティ(属性)と値のセットです。ここでは記事の見出し(タイトル)を示すheadlineプロパティに実際のタイトル文字列を設定しています。
公開日を示すプロパティです。値は日時をISO8601形式(YYYY-MM-DDなど)で記述します。
著者情報のプロパティです。値としてさらにオブジェクトが入り、@type: Person(人物であること)とname:サイト管理人(著者名)を指定しています。
このように、プロパティ(キー)と値をペアで記述していくことで、コンテンツのさまざまな情報を細かくマークアップできます。必要に応じて画像(imageプロパティ)や記事の概要(descriptionプロパティ)、カテゴリ(articleSection)など、多くの情報を付加できます。
構造化データを記述する際は、適切なボキャブラリー(schema.orgのタイプ)とプロパティを選ぶことが重要です。
例えば、レシピ記事なら”@type”:”Recipe”を使い、材料リストにはrecipeIngredientプロパティ、調理時間にはcookTimeプロパティを使う、といった具合です。schema.orgでは構造化データの各タイプとプロパティの詳細を確認できるため、正確なマークアップに役立ちます。
自分のコンテンツに合った構造化データの定義を選び、正確に記述しましょう。適切な構造化マークアップを施せば、検索エンジンに情報が伝わりやすくなり、SEOの向上につながります。
構造化マークアップはSEOに効果がある?(SEOへの影響)

構造化データを用いた構造化マークアップはSEOにおいて注目される施策ですが、その直接的な効果についてまず押さえておきましょう。
結論から言えば、構造化データをマークアップしたこと自体が検索ランキングを直接向上させることはないとされています。Googleの公式見解でも、構造化データの有無は現時点でランキング要因(直接のSEO評価項目)には含めていないと明言されています。したがって「構造化マークアップを入れたから急に検索順位が上がる」というものではありません。
しかし、構造化マークアップを実装することにより間接的にSEO効果を高める可能性があります。
理由は、構造化データによって検索結果に表示される内容がリッチになる(後述するリッチリザルトが表示される)ことで、ユーザーの目を引きやすくなりクリック率(CTR)が上昇しやすくなるためです。
クリック率が上がればサイトへの訪問者が増え、結果的にユーザー行動の改善や評価向上につながることがあります。また検索エンジンがページ内容を正しく理解できれば、適切なクエリで表示されたり、関連検索結果に掲載されたりといったチャンスも増えるでしょう。
つまり、構造化マークアップは「直接より間接的に」SEOにプラスの影響を与える施策と言えます。実装自体はサイトの土台を強化するテクニカルSEOの一環であり、それ単独で順位アップの魔法ではないものの、総合的な検索パフォーマンス改善につながる重要な要素です。
構造化マークアップのメリット
構造化マークアップを行うことで得られるメリットを整理してみましょう。SEOの観点も含め、大きく分けて次の2点が挙げられます。

メリット1|検索エンジンが内容を認識しやすくなる
構造化データにより、コンテンツが検索エンジンに構造化された状態で伝わりやすくなります。
ページ上のテキストを単なる文字列でなく「特定の属性を持つ情報」として認識させることで、クローラーが構造化されたデータとしてページ内容を正確に把握できます。
例えば、会社名・住所・電話番号といった情報を構造化マークアップしておけば、検索エンジンはそれらを構造化された企業情報として検索エンジンのデータベースに蓄積できます。検索エンジンにページを見つけてもらいやすくするだけでなく、ユーザーの検索クエリに対して適切な形でマッチさせる助けにもなります。
つまり、検索エンジンが内容を正しく認識できるという点は、SEOにおいても重要なポイントなわけです。
また、コンテンツを正しく認識してもらえると、Googleのナレッジグラフ(Knowledge Graph)や音声アシスタントへの応答など、検索エンジン内部でのデータ連携にもメリットがあります。結果として、自サイトの情報が様々な形で検索結果に活用される可能性が高まるのです。
メリット2|リッチリザルト(リッチスニペット)が表示される場合がある
もう一つの大きなメリットは、検索結果にリッチリザルト(Rich Result)として表示される可能性が生まれることです。リッチリザルトとは、通常の青いリンクと説明文だけの検索結果に比べて、画像や評価★マーク、Q&Aの展開ボタンなど視覚的・機能的に強化された検索結果表示のことです。
構造化データでページ内容をマークアップしておくと、Googleはそれを活用してユーザーにより有用な情報を直接検索結果上で表示してくれることがあります。この表示強化はSEO上も非常に有利です。
例えば、FAQ(よくある質問)の構造化データを設定すれば、検索結果に質問と回答のプレビューが折りたたみ表示されることがあります。レシピ記事で適切に構造化マークアップすれば、検索結果に料理の写真や調理時間、レビュー評価が表示され、ユーザーの目を引きます。商品ページなら価格や在庫状況、レビューの★評価が表示される場合もあります。
こうしたリッチリザルトが出現すると、検索結果一覧での存在感が増し、ユーザーが思わずクリックしたくなる魅力的な表示になります。
リッチリザルトによってCTR(クリック率)の向上が見込めるため、結果的にサイトへの流入増加やコンバージョン機会の拡大につながります。
したがって、構造化マークアップはユーザーへのアピールという点でも非常に重要なメリットを持っています。
このように構造化マークアップのメリットは、検索エンジンとユーザー双方に及びます。総合的に見てSEO施策としても大きな注目を集めています。
主な構造化データの種類と対応するリッチリザルト例

現在Google検索でサポートされている構造化データの種類は数多くあります。代表的なものをいくつか紹介しましょう。自分のサイトのコンテンツに当てはまるものがあれば、ぜひマークアップを検討すると良いでしょう。適切な構造化マークアップはSEOにもつながります。
-
記事(Article/NewsArticle/BlogPosting)
ニュース記事やブログ記事を対象とした構造化データです。タイトル・掲載日・著者・画像などをマークアップできます。検索結果では記事のタイトル下に公開日や著者名が表示されたり、ニュース記事であればトップニュース枠に表示されることもあります。
-
よくある質問(FAQPage)
Q&A形式のコンテンツを対象とした構造化データです。質問とその回答(Question・Answer)をマークアップします。実装すると、検索結果に質問項目が追加表示され、ユーザーがクリックすると回答がドロップダウン表示されます。ユーザーの疑問をダイレクトに解決できるため、結果としてサイトへの誘導につながるケースもあります。これによりSEOにも好影響が見込めます。
-
パンくずリスト(BreadcrumbList)
サイト内における現在ページの階層(パンくずナビゲーション)を示す構造化データです。ページがどのカテゴリ・ディレクトリに属しているかを構造化データとしてマークアップします。検索結果のタイトル上部に「サイト名 > カテゴリ名 > ページ名」といった形で表示され、ユーザーにとって現在地の把握がしやすくなります。
-
商品(Product)
商品ページ向けの構造化データで、価格・在庫状況・レビュー評価・SKUなどをマークアップできます。関連してレビュー(Review)やオファー(Offer)といったタイプも組み合わせます。正しく実装すれば、検索結果に商品価格やレビューの星評価数、割引情報などが表示されることがあり、購買意思決定に役立つ情報をユーザーに提供できます。構造化マークアップによって検索結果での視認性が上がり、SEOにも有利です。
-
レシピ(Recipe)
料理のレシピ記事向けの構造化データです。材料(ingredient)や手順、調理時間、カロリー情報、ユーザー評価などを詳細にマークアップできます。検索結果では料理の写真やレビュー星、調理時間などが表示され、料理を探しているユーザーの関心を引きやすくなります。また、手順を段階的に示すHowTo構造化データと組み合わせて、調理の各ステップを表示させることも可能です。
-
求人情報(JobPosting)
求人募集のページ向けの構造化データです。職種名、勤務地、給与、雇用形態、掲載期限などをマークアップします。実装すると、Googleの求人検索結果(Google for Jobs)にリッチなカード形式で自社の求人情報を表示できます。ユーザーは検索結果上で条件を確認でき、そのまま応募ページに進みやすくなります。
-
動画(VideoObject)
動画コンテンツ向けの構造化データです。動画のタイトルや説明、サムネイルURL、再生長さ、アップロード日時などをマークアップします。検索結果では動画のプレビュー画像や再生時間が表示され、場合によっては動画内のチャプター(ClipやBroadcastEventとして定義)ごとのプレビューがタイムライン表示されることもあります。ユーザーは動画を見る前に概要をつかめるため、興味を惹く効果があります。
-
ローカルビジネス(LocalBusiness)
店舗や企業のビジネス情報向けの構造化データです。住所、電話番号、営業時間、緯度経度、メニューURLなど様々な情報をマークアップできます。実装すると、検索結果のナレッジパネルやGoogleマップ上で企業情報が充実し、ユーザーが店舗の詳細(所在地や口コミ)を把握しやすくなります。特に店舗型ビジネスの場合は店舗スケジュール(OpeningHours)やメニューなどを構造化しておくと親切です。これらの情報を整理して構造化しておくことは検索経由の集客、つまりSEOにもつながるでしょう。
-
イベント(Event)
コンサートやセミナー、オンライン配信などイベント情報向けの構造化データです。イベント名、開催場所、日時、主催者、チケット情報などをマークアップします。検索結果ではイベントの日付や場所がリッチリザルトとして表示され、検索ユーザーが興味のあるイベントを見つけやすくなります。複数日程のイベントもまとめて表示可能です。
-
サイトリンク検索ボックス(Sitelinks Search Box)
ウェブサイト内検索用の検索ボックスを検索結果上に表示させるための構造化データです。自サイトに検索機能がある場合にその検索用URLをマークアップしておくと、Googleがメインのスニペット下にサイト内検索ボックスを表示してくれる場合があります。ユーザーはわざわざサイトに訪れなくても直接検索できるので、目的の情報に迅速にアクセスでき利便性が上がります。
上記は代表例ですが、他にも旅行や予約(FlightやBook)、教育(Course)など様々なスキーマタイプがあります。自社サイトの内容に応じて最適な構造化データを選び、正しく記述することで、検索結果での表示を充実させユーザーへのアピールにつながりましょう。
構造化データを実装・設定する方法(マークアップ手段)

構造化マークアップを自分のサイトに導入するには、いくつかの方法があります。ここでは主な3つの実装方法と、加えてCMSユーザー向けの方法について解説します。自分の技術レベルやサイト規模に合った方法を選ぶことがSEO上も重要です。
方法1|HTML上で直接マークアップする
最も基本的なやり方は、ページのHTMLソースコードに直接構造化データを記述する方法です。前述のJSON-LDの例のように、<script>タグを使ってマークアップを埋め込んだり、Microdata形式で各所に属性を書き込んだりします。
この方法のメリットは、構造化の細部まで自分でコントロールできる点です。各ページに構造化データを用いたマークアップを施す際は、適切なボキャブラリー(schema.orgのタイプ)とプロパティを調べて記述していけば、非常にきめ細かいマークアップが可能です。
しかしその反面、専門的な知識と労力が必要になります。全ページのHTMLを編集するには手間がかかりますし、記述ルールや使えるプロパティを理解していないと正しいマークアップができません。また、一つひとつ手作業になるため、大規模サイトでは現実的でない場合もあります。
基本的に技術的な理解がある場合は直接HTMLに書き込む方法でも問題ありません。これは典型的なテクニカルSEOの手法でもあります。特に静的なサイトやページ数が少ないサイト、小規模なブログなどでは手動で実装してもよいでしょう。その際はGoogleがサポートするボキャブラリー(主にschema.org)とシンタックス(JSON-LD推奨)で記述することを忘れないようにしてください。公式のガイドラインに従った正確なマークアップが重要です。
方法2|構造化データ マークアップ支援ツールを使う
コードを自分で書くのが難しい場合や効率化を図りたい場合、Google公式の「構造化データ マークアップ支援ツール」を使う方法があります。これはGoogleが提供するGUIベースのツールで、画面上の指示に従ってクリック操作するだけで構造化マークアップ用のHTMLコードを自動生成してくれる便利なものです。
構造化データ マークアップ支援ツールの使い方
- ツールのページにアクセスし、マークアップしたい自サイトのページURLを入力します。
- ページの種類(記事、商品、イベントなど該当するデータタイプ)を選択します。
- 「タグ付け開始」をクリックすると、選択したページのプレビューが表示されます。
- プレビュー上でマークアップしたいテキスト要素を選択し、「これはタイトル」「これは画像」など対応する項目を選んでタグ付けしていきます。
- 必要な項目をすべてタグ付けできたら、「HTMLを作成」をクリックします。
- 構造化データが組み込まれたHTMLコードが生成されるので、そのコードをコピーして自分のサイトに反映します(通常は生成された<script type=”application/ld+json”>タグをコピーしてページのHTMLに貼り付けます)。
このツールを使えば、自分でプロパティ名を調べたりJSONを書く手間が省けます。
例えばブログ記事のページであればタイトルや公開日、著者名などを順番にクリックして指定するだけで、自動的に適切なJSON-LDが生成されます。プログラミング知識がなくても扱いやすいのが利点です。
注意点として、このツールを使うにはGoogleサーチコンソールへのサイト登録(所有権確認)が必要です。自サイトをサーチコンソールに追加し、所有者として確認されていないと利用できません。また、このツールは1ページずつ手動で設定する形になるため、多数のページに実装する場合は効率が落ちることもあります。その場合は後述のプラグイン利用なども検討しましょう。
方法3|データハイライターを使用する
Googleサーチコンソールにはもう一つ、ツールの一種である「データハイライター」という機能があります。これはページ上のコンテンツを強調表示して構造化データとしてGoogleに伝えるためのツールです。方法2のマークアップ支援ツールと同様にサーチコンソール上で操作しますが、大きな違いはサイトのHTMLコード自体を変更せずに構造化データを教える点です。
データハイライターの使用手順も概略を示すと次のようになります。
データハイライターの使用手順
- サーチコンソールのデータハイライターを開き、構造化データを設定したいページ(またはページのパターンとなるURL)を指定します。
- データタイプ(記事、イベント、地元のお店、レストラン、商品、ソフトウェアアプリ、映画、テレビ番組のエピソード、書籍の計9種類)から該当するものを選びます。
- 該当ページのプレビューが表示されるので、あとは支援ツールと同じようにマウスでテキストを選択し「これはタイトル」「これは日付」等タグ付けしていきます。
- 必要事項をハイライトできたら保存し、Googleに提出します。
データハイライターを使用すると、Googleはその指定に基づいて自動的にサイトの該当ページ(または類似ページ全部)を巡回し、構造化データを解釈してくれます。HTMLに手を加えなくても良いため、サイト運営者側は、手軽に構造化を実現できるというメリットがあります。
ただし、データハイライターには注意点もあります。
まず、Googleのクローラーが既に認識しているページでしか使えないという点です。公開したばかりで未クロールのページには適用できないので、その場合はマークアップ支援ツールなどを使う必要があります。
また、データハイライターはあくまでGoogle専用の簡易手段なので、構造化データが実際にページHTMLに埋め込まれるわけではありません。他の検索エンジン(Bingなど)には効果が及ばない可能性があります。より包括的なSEOを考えるならば、可能であれば最終的にはHTML自体に構造化データを組み込むのが理想です。
方法4|CMSやプラグインの機能を活用する
WordPressなどのCMSを使ってサイトを運用している場合は、CMSやプラグインの持つ機能で構造化データを出力する方法も有効です。現在多くのCMSではSEO対策の拡張やテーマ側の機能として、構造化データに対応している場合があります。
例えば、WordPressのSEOプラグインである「Yoast SEO」や「All in One SEO Pack」などは、サイトの基本情報(サイト名やロゴ、会社情報)や記事の構造化データ(ArticleのJSON-LD)を自動生成して挿入してくれます。また、パンくずリスト用の構造化データもプラグイン経由で簡単に出力可能です。Gutenbergエディター(ブロックエディター)で提供されているFAQブロックや問い合わせフォームブロックなどを使えば、裏側で適切な構造化データ(FAQのQAPageスキーマなど)が付与されます。
さらに近年人気の高い有料テーマでは、構造化データ対応が強化されています。
例えば、WordPressテーマ「SWELL」では、ブロックエディターから追加された情報は、構造化マークアップの形式で自動出力される仕組みがあり、レビューやFAQも適切に検索エンジンへ伝達できます。つまりCMSの設定画面やブロックを操作するだけで構造化マークアップが完了するため、初心者でもミスなく導入できるのです。
CMSやプラグインを使う方法の利点は、手間が大幅に省けることと更新に追随しやすいことです。記事を投稿する度に自動で構造化データが付くので入れ忘れやミスが起こりにくく、サイト規模が大きくなっても構造化データを統一的に管理できます。サイト全体で構造化データを統一できるため、SEO対策上も有効です。ただし導入するプラグインやテーマによっては出力されるデータの種類が限られるため、もし特殊なスキーマが必要な場合はカスタマイズが必要になることもあります。
ご自身がCMSを利用している場合は、まず既存のテーマやプラグインでどこまで構造化データ対応ができているか確認してみましょう。何も対応していない場合でも、適切なプラグインを導入すれば比較的簡単に構造化マークアップを実現できます。
構造化データ実装後の確認・テスト方法

構造化マークアップを実装したら、正しく記述できているかテストすることが重要です。誤ったマークアップは効果が出ないばかりか、検索結果にエラー表示されたりGoogleから構造化データの評価を下げられたりする可能性もあります。
つまり、構造化データの誤りはSEOの面でもマイナスとなりかねません。代表的な構造化データの検証ツールを2つ紹介します。これらを活用してミスのない実装を心がけましょう。
ツール1|スキーママークアップ検証ツール(Schema Markup Validator)
構造化データの標準規格を推進するschema.orgが提供する検証ツールです。旧Google構造化データテストツールの役割を引き継いだもので、構文と文法の正確性をチェックできます。Schema Markup Validatorでは、サイト上に埋め込まれているすべての構造化データ(schema.orgベース)の記述が検証対象になります。
Schema Markup Validatorの使用手順
- Schema Markup Validatorのページを開く。
- 検証したい自分のページのURLを入力する(または直接構造化データのコードを貼り付けても可)。
- 「テストを実行」をクリックする。
- 結果が表示され、エラーがなければ「エラーなし」「警告なし」と表示されます。もし構造化内容に誤りがある場合、エラー箇所と内容がリストアップされるので修正しましょう。
このツールはGoogleに限らずschema.orgの仕様準拠チェックなので、Googleが検索結果で利用しない種類のスキーマも含め確認できます。基本的には「自分の書いたマークアップに文法的誤りがないか」を広範囲にチェックする目的で使うと良いでしょう。このステップはSEOにおいても非常に重要です。
ツール2|リッチリザルトテスト
Googleが提供する公式のリッチリザルトテストも必ず活用しましょう。リッチリザルトテストでは、入力したページにGoogleの検索結果でリッチリザルト対象となる構造化データが含まれているかを検証できます(旧構造化データテストツールは提供終了し、現在はこちらに統合)。
リッチリザルトテストの使用手順
- リッチリザルトテストのページにアクセスする。
- 検証したいページのURLか、構造化データを含むHTMLコードを入力する。
- 「テスト」ボタンをクリック。
- 数秒待つと結果が表示されます。問題なく実装できていれば「このページはリッチリザルトの対象です」といったメッセージが出ます。対応しているリッチリザルトの種類(例:FAQ、Breadcrumbなど)や検出された項目も一覧で表示されます。
- もし構文エラーや必須項目の不足がある場合は、エラー内容が詳細に表示されます。該当箇所を修正して再テストしましょう。
リッチリザルトテストはGoogleがサポートしているスキーマに限定してチェックを行う点に注意してください。
例えば、構造化データ自体は記述されていてSchema Markup ValidatorではOKでも、Googleが検索結果で利用しない種類のスキーマ(たとえば独自拡張のスキーマなど)の場合、「リッチリザルトの対象ではありません」と表示されることがあります。主に自分が狙ったリッチリザルトが正しく出るかの確認に使うと良いでしょう。特定のリッチリザルト(FAQやレビュー星など)が出ない場合、エラー箇所を修正して再テストし、正しく「有効」になるまで調整することが重要です。
問題なく実装できていればリッチリザルトが有効である旨のメッセージが出ます。これは検索結果にリッチリザルトが表示されている状態であり、SEO上望ましい状態と言えます。
成果にコミットするSEOコンサルティングなら
フリースクエアにお任せください!
豊富な実績とインハウス(内製化)支援も可能!
まとめ

構造化マークアップについて、その概要から具体的な実装方法・ツール活用術まで詳しく解説しました。最後に要点を整理します。
-
構造化マークアップとは
Webページの内容に対して「これは何の情報か」を示す追加の記述を行うこと。検索エンジンにコンテンツの意味を伝える技術であり、HTMLにメタデータを追加して情報を構造化するイメージです。
-
構造化データの種類
主な構造化データの記述形式として、Microdata、RDFa、JSON-LDの3種類があります。GoogleはJSON-LD形式を推奨しており、現在はJSON-LDでの実装が一般的です。いずれもschema.orgといったボキャブラリーを使ってタイプとプロパティを定義します。
-
SEOへの効果
構造化データを活用した構造化マークアップは、直接の順位アップ要因ではありませんが、リッチリザルトの表示を通じてクリック率向上など間接的にSEO効果をもたらします。検索エンジンにも内容を理解してもらいやすくなるため、結果的に有利に働くことがあります。
-
マークアップの具体例
JSON-LD形式のコードで記事や商品などをマークアップ可能です。例として記事のタイトル・公開日・著者を構造化するコードも紹介しました。各種コンテンツ(レシピ・イベント・動画など)に応じて適切なスキーマを選び、プロパティと値のペアで詳細情報を記述します。
-
主なリッチリザルトの種類
記事、FAQ、パンくずリスト、商品、レシピ、求人、動画、ローカルビジネス、イベント、サイトリンク検索ボックスなど多数あります。自サイトに関連する構造化データを活用したマークアップを実装すれば、検索結果での表示がリッチになりCTR向上が期待できます。
-
実装方法
直接HTMLにコードを記述する方法のほか、Googleのマークアップ支援ツールで自動生成したり、サーチコンソールのデータハイライターでタグ付けしたりする方法があります。WordPress等のCMS利用者はプラグインやテーマ機能による自動構造化も活用できます。自分の技術レベルやサイト規模に合った方法を選ぶことがSEO上も重要です。
-
検証とテストの重要性
構造化データを入れたら、リッチリザルトテストやSchema Markup Validator、サーチコンソールを使って正しくマークアップできているか必ず確認しましょう。エラーを放置するとSEO効果が出ないばかりか、構造化データが正しく反映されず検索結果への表示にも悪影響を及ぼします。SEOの効果も得られなくなってしまいます。構造化マークアップの完成度を高めるために、テストと修正を繰り返すことがSEO対策としても大切です。
構造化マークアップは一見ハードルが高い印象を受けるかもしれませんが、ツールやプラグインを活用すれば初心者でも取り組めるSEO施策です。リッチリザルトの恩恵は大きく、競合サイトとの差別化にもつながります。ぜひこの機会に自分のサイトにも構造化データの導入を検討してみてください。適切な構造化マークアップによって、検索エンジンとユーザー双方に伝わりやすいコンテンツを提供し、SEO効果を高めていきましょう。
WRITER

ライターMT
ライターMTの記事一覧複数メディアのSEO対策担当者を8年以上経験。SEO知識の他に、健康、脱毛、恋愛、コンプレックスなどのジャンルも得意。これまで500本以上のコンテンツ制作と上位表示実績を持つ。
キーワード選定からライティングまでを一貫して行うため検索意図を把握する能力が高い。
構造化マークアップとは?SEOの効果や書き方をわかりやすく解説
この記事が気に入ったら
いいね!しよう