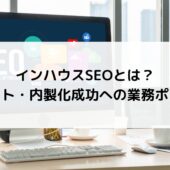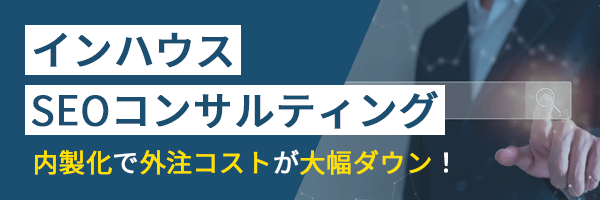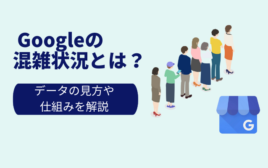- 2025.7.16
- SEO
Webサイト改善で成果を出す方法や重要ポイントを徹底解説

現代のビジネスにおいて、自社のWebサイトの改善は欠かせない取り組みです。Webマーケターや企業のWeb担当者にとって、サイトから安定してリード獲得や売上、CV(コンバージョン)を生み出すためには、サイトを「作って終わり」にせず、継続的に最適化していく必要があります。
また、サイト改善では自社サイトが達成すべき目的を明確にし、その達成に向けて継続的に成果を高めていくことが求められます。
目的達成に向けたCVを最大化するためのWebサイト改善の意義や基本的な進め方、具体的な改善ポイント、活用すべき分析ツール、そして成功事例と失敗しないためのポイントについて詳しく解説します。ぜひ自社サイト運営の参考にしてください。
結果が違う本格SEO運用代行なら
フリースクエアにお任せください!
プロのSEO運用代行を低コストで実現!
目次
Webサイト改善とは?なぜ必要なのか

Webサイト改善とは、公開中のWebサイトに対して分析に基づいた修正・最適化を継続的に行い、サイトのCVや目的達成率を高めていくことです。単なるデザイン変更やリニューアルとは異なり、ユーザー行動データやマーケティング施策の効果測定に基づき、課題を発見・改善していくプロセスを指します。
Webサイトは一度作って終わりではなく、設定した目的に向けて運用しながら成果を出し続けるために改善を続ける必要があります。Webサイト改善を行うことで得られる主なメリットには次のようなものがあります。
-
リード獲得数や売上の向上
サイト上でユーザーに商品の魅力が伝わりやすくなり、資料請求や商品購入といったCV増加が期待できます。また、コンテンツの質を上げて検索エンジンで上位に掲載されれば流入増にもつながります。
-
ユーザー体験(UX)の向上
サイトの使い勝手が良くなれば顧客体験が向上し、滞在時間の延長やサイトから離れる割合の減少につながります。ユーザーが目的の情報をスムーズに得られるサイトは、結果的に企業への好印象や信頼性アップにも寄与します。
このように、Webサイト改善はビジネス成果の向上(売上・CV増)とユーザビリティ向上(顧客満足度向上)の両面で大きな意味を持ちます。ただし、闇雲に改修すればよいわけではありません。次に、Webサイト改善で陥りがちな失敗パターンを確認し、成功のために避けるべきポイントを押さえましょう。
Webサイト改善が失敗するよくある原因

よくある失敗パターンをまとめましたので、当てはまるものがないかチェックしてみてください。
-
目的やKPIを整理せずに闇雲に改修してしまう
サイトの目的やKPIを明確にせずに改修してしまうと、コストばかりかかりCVにつながらないサイト改善になりがちです。まずWebサイトの役割や達成したい目的をはっきりさせることが必要です。
-
データ分析をせず勘や思いつきだけで変更してしまう
現状の課題の原因を分析せずに「とりあえずデザインを変えてみる」等の対応は的外れになる場合が多いです。過去の経験や担当者の勘に頼った改修も、環境変化の中では失敗しやすいと言えます。
-
ユーザー視点を欠いた改善を行っている
コンバージョンが出ないからといって、強引にポップアップを出したり派手なアニメーションでCTAを目立たせたりしてしまうと、CVどころかユーザビリティを損ない逆効果です。常にエンドユーザーの視点に立ち「使いやすいサイト」になるよう考えましょう。
-
見た目のリニューアルだけで満足してしまう
Webサイト改善というとデザイン刷新を思い浮かべる方もいます。しかし見た目を変えるだけでは成果向上は望めません。見栄えよりも内容や導線の改善が本質であることを忘れないようにしましょう。
-
他社の成功事例をそのまま真似してしまう
トレンドや他社事例を参考にするのは良いことですが、そのまま模倣してもうまくいくとは限りません。自社の業種・ターゲット・課題に合わせてカスタマイズした施策でないと、期待したCVも得られない可能性があります。
-
SEOや広告など集客施策と切り離して考えている
Webサイトはマーケティング全体のハブです。Webサイト自体の改善と同時に、検索エンジンや広告からの流入設計まで考慮しないと、せっかくの改善が集客に貢献しない恐れがあります。例えば、流入キーワードとページ内容のミスマッチはユーザーがページを離れる原因になります。
以上のような失敗要因を踏まえれば、Webサイト改善では「目的の明確化」と「データに基づくユーザー視点の施策」が何よりも大切だと分かります。それでは具体的に、成果を出すためのWebサイト改善の進め方を見ていきましょう。
Webサイト改善を成功させる進め方

効果的にWebサイトを改善するには、PDCAサイクルに沿った計画的なアプローチが欠かせません。ここではサイト改善の基本ステップを順に追って解説します。自社サイトの状況に照らし合わせながら、一つひとつ着実に進めていきましょう。
1.サイトの目的・KPIを明確に
改善に着手する前に、まずサイトの目的やKPIをはっきりさせることがスタート地点です。
自社サイトで達成したいゴール(例:お問い合わせ件数〇件/月、EC売上〇円/月など)を具体的に設定しましょう。BtoBサイトなのかECサイトなのかによって目的は異なりますが、「資料請求の獲得」「商品購入」「自社ブランドの認知度アップ」など、Webサイトごとに果たすべき役割があります。
現状でその成果が思うように上がっていない場合は、何が課題となっているかを洗い出します。それがそのままサイト改善の課題設定となります。例えば「アクセスはあるのに問い合わせにつながっていない」のか、「アクセス自体が少ない」のか、「既存顧客の再訪問・追加購入が少ない」のか、課題によって取るべき改善施策や分析方法も変わってきます。
また、Webサイトの目的と合わせてターゲットユーザー像の整理も大切です。誰に何を提供するサイトなのかが不明確だと、施策の方向性も定まりません。ペルソナ設定を行い、ターゲットユーザーのニーズとWebサイトの目的を擦り合わせておきましょう。
2.データを計測・分析して現状を把握
目標を定めたら、次に現状のWebサイトのパフォーマンスをデータで分析するステップに入ります。主観ではなく客観的なデータに基づいて現状把握することが大切です。
まずはアクセス解析ツールを導入し、CVの動きを可視化することから始めましょう。Googleアナリティクス(GA4)やヒートマップツール等を使えば、サイト内の各ページの閲覧数やユーザー属性、どのボタンがクリックされているかなど、多角的なデータが収集できます。
これらのツールをWebサイトに設置し、十分なサンプルデータが蓄積されるのを待ってから分析を行います。
アクセス解析ツールでは、どのページがよく見られているか、コンバージョンに至っているか、直帰率が高いページはどこか等を把握できます。こうしたデータに基づき、まずは現状の課題を数字で洗い出すことが必要です。
見るべき指標の例としては、以下のようなものがあります。
-
コンバージョン率(CVR)
サイト訪問者のうち目標行動(問い合わせ送信や購入等)に至った割合。主要なコンバージョンページでCVRが低ければ、そのページの内容や導線に問題がないか分析します。
-
滞在時間
ページに留まっている時間。極端に短い場合は内容の関連性やファーストビューに問題があり、逆に非常に長い場合はページ内容が分かりにくい可能性があります。
また、サイト全体のCV数(例えばお問い合わせ件数や購入件数など)が目標に達しているかどうかも大切な指標です。改善によってCV数が増加すれば、Webサイト全体としての成果向上が実感できます。
3.データから課題を抽出
分析データが揃ったら、次はその結果にもとづいて現状の課題を言語化します。数字が示す傾向から「どこに問題があるのか」「ボトルネックは何か」を洗い出す作業です。
いくつか着目ポイントを挙げておきます。
-
CV率が低いページはどこか?
コンバージョン率(CVR)が低い場合、該当ページの内容や導線(CTA配置やフォーム仕様)に課題がないかチェックします。ユーザーにとって有益な情報を提供できているか、適切な場所にわかりやすいCTAボタンがあるか、フォームが使いにくくないか等を点検しましょう。
-
直帰率が高いページはどこか?
ユーザーが最初に着地するページでサイトを離れてしまう割合が高い場合、ユーザーの検索意図や目的に応えていない可能性があります。特にランディングページ(最初の閲覧ページ)の内容が検索キーワードや広告の訴求内容と合致しているかを確認しましょう。ヒートマップツールを活用すれば、ページ内のどの部分でユーザーが離れてしまうかも分析できます。
-
流入経路ごとのパフォーマンスは?
流入チャネル別にデータを比較すると、新たな発見が得られる場合があります。例えば広告経由の訪問で直帰率が高い場合、広告文と着地ページの内容に齟齬があるかもしれません。その場合、広告のクリエイティブ改善やランディングページの調整といった施策も見えてきます。
このようにデータを多面的に読み解き、サイトのどの部分にどんな課題があるかを明確にしていきます。課題が特定できたら、次はいよいよそれを解決するための施策を考えましょう。
4.改善施策を立案し、優先順位をつける
課題がはっきりしたら、それぞれに対して具体的な改善アイデア(施策)を出していきます。ブレインストーミングなどで考えつくだけアイデアを洗い出した後、CVへのインパクトと実施コストを踏まえて優先順位を決めていきます。
施策ごとの必要リソース(工数や費用)も考慮します。すぐ実行できるテキスト修正やレイアウト調整などの「小さな改善」は早期に着手し、デザイン全面改修やシステム変更を伴うような「大きな改善」は計画的に長期で検討するといった具合に、リソース配分も計画しましょう。
施策の優先度判断にはインパクトと実現容易性のマトリクスを使う方法も有効です。効果が大きく実行も簡単な施策から手を付け、効果大だが工数も大きいものは計画立てて順次対応、効果小・工数大のものは思い切ってやらない、といったメリハリをつけることが必要です。
5.改善策を実行
優先度の高い改善策から順に、具体的なWebサイト修正・改善作業を実行に移します。この際、一度にあれもこれもと多数の変更を同時進行で行うのは避けましょう。一度に複数の施策を実施してしまうと、どの施策が効果につながったのか検証しにくくなるためです。基本は一つずつ施策を実装→検証のサイクルで進めることをおすすめします。
実行にあたっては、開発チームやデザイナーとも連携し、変更内容を正確に反映させます。テキスト差し替えや画像変更など小さな修正でも、意図した改善効果が得られるよう細部まで注意しましょう。
必要に応じてCV向上を目的としたA/Bテストを活用するのも有効です。たとえば新旧デザインでCVRを比較検証することで、変更の有効性を定量的に判断できます。近年はノーコードでA/Bテストを実施できるツールもありますので、リスクを抑えて改善を図りたい場合に検討すると良いでしょう。
6.効果測定し、改善を継続(PDCAサイクル)
最後に、実施した改善策の効果検証(モニタリング)を必ず行います。施策実行前後で主要指標(CVRやCV数、直帰率など)がどう変化したかを計測し、当初の仮説が正しかったか、期待通りの成果が得られたかを検証しましょう。
効果測定のポイントは、十分な期間とデータをもって判断することです。施策によってはすぐに結果が出ない場合も多いため、一定期間運用した上で数値を比較します。改善前後のデータを比較し、うまくいった点・いかなかった点を整理したら、学びを次の施策に活かします。
このようにしてPDCAを回しながら、Webサイト改善を継続していくことが大切です。成果に満足せず、定期的にデータをチェックして新たな課題が出てきたらまた改善策を考えて実行する。このサイクルを回し続けることで、Webサイトは少しずつ理想の形に近づき成果を伸ばしていくことができます。
「サイトに手を加えてみて、成果が改善すればOK、落ちたら元に戻す」というシンプルな思考で構いません。場当たり的ではなく仮説に基づいた行動であれば、トライ&エラーを繰り返す中で必ずサイトは良くなっていきます。
それでは次に、具体的にWebサイトのどの部分を改善すべきか、注目すべき代表的なポイントを見ていきましょう。
Webサイトの主な改善ポイント

Webサイト改善の効果を最大化させるには、成果につながりやすい箇所から優先的に手を入れることが基本です。どこを改善すべきかはサイトごとの課題によって異なりますが、一般的によく見直しが行われる主要ポイントがあります。ここでは代表的な改善箇所を紹介します。
ファーストビューの最適化
ファーストビューとはユーザーがサイトに訪れて最初に目にするページ上部の画面領域のことです。
訪問者はこのファーストビューを一目見て「自分の求める情報がありそうか」「使いやすそうか」を瞬時に判断します。ファーストビューで興味を引けないと、その後ユーザーはサイトをすぐに離れてしまうため、どんなに他の部分を改善しても成果に繋がりにくくなります。まずはファーストビューが適切かどうか見直しましょう。
改善のポイントは、端的で魅力的なメッセージとビジュアルを配置することです。
ユーザーが求めている価値提案を見逃さないよう、大見出しやキャッチコピーで明示します。例えば製品サイトであれば「〇〇が簡単にできるツール」など、提供価値がひと目で伝わるコピーを配置します。また主要なCTA(例えば「無料で試す」ボタンなど)がファーストビューに含まれていると、ユーザーの行動を促しやすくなります。
デザイン面でも、読み込み速度が速く視覚的にごちゃごちゃしないレイアウトにします。ファーストビューで伝える情報が多すぎてもユーザーは混乱します。シンプルに「あなたに〇〇を提供します」と伝え、続きはスクロールして詳細を読んでもらえるよう誘導させる構成が望ましいでしょう。
ナビゲーションと内部導線の改善
Webサイト内でユーザーが必要な情報にたどり着きやすい導線になっているかも大切なチェックポイントです。主なページへのアクセスが少ない場合や回遊率(サイト内で複数ページを閲覧する率)が低い場合は、サイトのナビゲーションやリンク設置に問題があるかもしれません。
改善策としては、ユーザー視点で「次にどのページへ行けばいいか」がわかるようにメニューやリンクを整理・強調することが挙げられます。具体的には次のような施策があります。
- ヘッダーメニューを常に画面上部に固定し、主要カテゴリへいつでも移動しやすくする。
- コンテンツページ下部やサイドバーに、関連する記事や製品ページへのリンクを設置して回遊を促す。
- ユーザーが「もっと詳しく知りたい」と感じそうな箇所に、詳細説明ページへの導線を設置する。
例えば、ブログ記事であれば関連記事リンク、製品紹介ページであれば料金やお問い合わせページへのボタンなど、ユーザーの次のアクションを考えた導線を用意しましょう。内部リンクのテキストもわかりやすく(例:「事例をもっと見る」など)、クリックしやすいデザインにすることが大切です。
コンテンツ内容と情報設計の見直し
Webサイトのコンテンツ(文章や画像、動画など)の質や構成も、成果に直結する不可欠なポイントです。ユーザーの目的に合った情報がしっかり提供されているか、分かりやすく伝わっているかを見直しましょう。
まず、コンテンツ内容がユーザーのニーズにマッチしているかを検討します。
ユーザーは何らかの課題解決や目的達成のために検索しサイトを訪れています。例えばユーザーが期待する内容とズレた場合、ユーザーはすぐにサイトを離れてしまいます。特にランディングページでは、検索キーワードや広告の訴求内容からユーザーが期待する情報を推察し、そのニーズに合致したコンテンツを盛り込む必要があります。例えば広告で「格安プラン」と謳っているのにLPに価格情報が無い、といったミスマッチは避けましょう。
次にコンテンツの読みやすさ・分かりやすさです。
文章量が多いサイトでは、構成や書き方次第で読了率が大きく変わります。改善すべき典型例は「見出しがなく長文がだらだら続く」「専門用語だらけで難解」といったケースです。段落ごとに適切な見出しを付ける、文章を簡潔にする、箇条書きを活用する、といったWebライティングの基本を押さえましょう。特にスマートフォンでは長文は読まれにくいので、短く区切った読みやすい文章を心がけてください。
また、掲載すべき情報が漏れていないかも確認しましょう。
商品やサービス紹介なら「機能・スペック」「料金」「導入方法」「FAQ(よくある質問)」などユーザーが知りたい事項が網羅されているかチェックしましょう。例えばよく問い合わせを受ける質問があるなら、それをFAQコンテンツとしてサイト上に充実させることでユーザーの不安解消と問い合わせ工数削減の両方に効果があります。
CTA(コールトゥアクション)の改善
CTA(Call To Action)とはユーザーに起こしてほしい行動を促すためのボタンやテキストのことです(例:「資料ダウンロード」「お問い合わせ」ボタン)。CTAが目立たなかったり文言が分かりにくかったりと、ユーザーがせっかく商品やサービスに興味を持っても行動に移れないまま離れてしまいます。
CTA改善のポイントは配置場所・デザイン・文言です。
CTAボタンはユーザーの視線に入りやすい位置に配置し、色やサイズも他の要素より目立つよう工夫します。ただしポップアップの多用など過度に目障りな演出はかえって逆効果なので注意が必要です。あくまでユーザーの利便性を損なわない範囲で強調しましょう。
文言も大切です。
ただ「お問い合わせ」と書くだけでなく、ユーザーにとってのメリットが伝わる一言を添えると効果的です。例えば、「3分で登録完了!無料で問い合わせる」といった具体的なメリットや所要時間を付記すると、ユーザーの心理的ハードルが下がります。実際、CTA近くにユーザーのメリットを記載するとCVRが上がる場合があります。
また、文言はユーザーが次に何をすればよいかを明確に示すことも大切です。
例えば問い合わせCTAなら「○○について相談する」「見積もりを依頼する」と具体的に書くことで、クリック後のイメージが湧き行動につながりやすくなります。デザイン・文言ともに複数案を試し、どれが最も反応が良いかA/Bテストで検証しながら最適化すると良いでしょう。
入力フォームの改善(EFO)
お問い合わせや資料請求、購入手続きなどの入力フォームは、ユーザーにとってストレスのない使いやすさが求められます。フォームの最適化はEFO(Entry Form Optimization)と呼ばれる主要な改善手法です。
フォームでよくある問題は、「入力項目が多すぎる」「エラーメッセージが分かりにくい」「スマホで入力しづらい」といった点です。必要以上に詳細な個人情報入力を求められるとユーザーは尻込みしてしまい、途中でやめてしまいます。
改善策としては入力項目を必要最低限に減らすことが第一です。
「この情報は本当に必要か?」を見直し、不要不急な項目は思い切って削除しましょう。
次にフォームのUI/UXです。
たとえば必須入力項目が分かりにくかったり、誤入力時のエラーメッセージが曖昧だったりだとユーザーは戸惑います。必須項目には「※必須」と明示し、エラー時にはどこが間違っているか具体的なメッセージで知らせるようにします。また一度入力した内容がエラーでリセットされてしまう仕様などは大きなストレスなので避けるべきです。
さらにスマートフォンからの入力のしやすさも大きなポイントです。
スマホ画面では入力欄の大きさやキーボードの種類指定(メール欄では@を入力しやすいキーボードを出す等)に配慮しましょう。最近はモバイル最適化されたフォームが当たり前になりつつあります。自社サイトのフォームが古いままの場合は早急に改善を検討してください。
EFOの効果検証には、フォームの送信率(開始したユーザーのうち完了した割合)を追跡します。
改善前後でこのCVRが向上すれば成功です。また、フォーム最適化の専門ツール(例:フォーム分析ツール)が提供されている場合、それらを活用してボトルネックを特定するのも有効でしょう。
ページ読み込み速度の改善
ページの読み込み速度(ロード時間)はユーザー体験・SEO双方の観点から極めて大切な要素です。
読み込みが遅いサイトはそれだけでユーザーがサイトを離れる原因になります。「クリックしたのになかなかページが読み込まれないので、訪問をやめてしまった」という経験は誰しもあるでしょう。特にモバイル回線ではシビアで、数秒待たされただけで「もういいや」と閉じられてしまうケースも珍しくありません。
読み込み速度改善の基本は、ページの軽量化です。
もっとも手軽にできるのは画像ファイルの最適化(圧縮)でしょう。画像はWebページを遅くする主犯になりがちです。「画像 圧縮」で検索すれば無料で画像を圧縮してくれるサービスが多数見つかります。大きな画像をアップロードしてそのままページに配置している場合は、適切なサイズにリサイズ&圧縮して差し替えるだけでもLCP(最大コンテンツ描画時間)など速度指標が改善する可能性が高いです。
また、不要なスクリプトやプラグインの削除、サーバーの応答速度改善(高性能サーバーへの移行やCDN導入など)も有効な場合があります。
サイトの構造が複雑であれば、遅延の原因となっている要素を洗い出して適切に対処しましょう。
現在のページ読み込み速度を把握するにはGoogleの「PageSpeed Insights」ツールが便利です。
URLを入力するだけで、モバイル/PCそれぞれの速度スコアと改善提案を提示してくれます。「どの画像が遅延要因か」「JavaScriptのどの処理に時間がかかっているか」まで診断可能なので、ぜひ活用してください。ページ速度はSEOランキングにも影響すると公表されていますので、ユーザーのためだけでなく検索評価のためにも取り組む価値があります。
モバイル対応の強化
近年ではスマートフォンからのアクセスが大半というサイトも珍しくありません。それにもかかわらずモバイル対応が不十分なサイトは、大きな機会損失につながります。モバイル対応(レスポンシブデザインやモバイル専用ページの用意)ができていない場合、スマホユーザーにとって使いにくいサイトとなり直帰率が高まってしまいます。またGoogleはモバイルフレンドリーかどうかを検索順位の評価基準に含めています。モバイル対応は今や必須と言えるでしょう。
対応すべきポイントは次のとおりです。
-
画面サイズに応じたレイアウト
小さいスマホ画面でも横スクロールなく閲覧でき、文字も拡大せず読めるようにする(レスポンシブWebデザインの適用)。
-
タップ操作への最適化
ボタンやリンクは指で押しやすい大きさ・間隔を確保する。フォーム入力もスマホで行いやすいよう配慮(前述のキーボード種類指定など)。
-
不要なモバイル非対応要素の除去
Flashコンテンツなどモバイルで表示できない要素がないか確認し、あれば削除・置き換えする。
-
モバイルページ速度の改善
モバイル回線環境でも快適に閲覧できるよう、ページ速度をできるだけ高速化する(画像圧縮、コード最適化等)。
自社サイトがモバイル対応できているかは、Googleサーチコンソールの「モバイルユーザビリティ」レポートや「モバイルフレンドリーテスト」ツールでチェック可能です。エラーが出る場合は指摘に従い修正しましょう。スマホファーストの視点でサイトを見直すことで、新たに気づく改善点も多いはずです。
代表的なサイト改善ポイントを挙げました。
もちろんサイトによって他にも見るべき箇所はありますが、まずはこれら基本項目の最適化から着手すると少ない工数でもCV改善に直結しやすいため、効果が出やすいでしょう。「自社サイトではどの部分に課題がありそうか?」を洗い出し、優先順位をつけて改善に取り組んでみてください。
サイト改善に役立つ分析方法・ツール

効果的なWebサイト改善の裏には、的確な分析とツールの活用があります。ここではWeb担当者に馴染み深い主要なツールや分析手法を紹介します。いずれも基本的なものですが、上手く使いこなすことでWebサイト改善の精度とスピードが格段に向上します。
主な無料分析ツール一覧
まずは無料で利用できる代表的なツールとその用途を整理します。
-
Google アナリティクス 4(GA4)
Google提供のアクセス解析ツール。サイト訪問者数、ユーザー属性、ページビュー数、CV数などサイト内でのユーザー行動を幅広く計測できます。2023年7月より従来のユニバーサルアナリティクスに代わってGA4へ完全移行しました。AIによる分析機能も備わっており、Webサイト分析の主軸ツールと言えます。まだ導入していない場合は必ず導入しましょう。
-
Google サーチコンソール
Google提供の検索パフォーマンス解析ツール。ユーザーがどんな検索クエリでサイトにアクセスしているか、検索結果での表示回数やクリック率、平均順位などが分かります。またモバイルフレンドリーテストやインデックスカバレッジのエラー確認など、サイトの技術的健全性チェックにも必須です。
-
ヒートマップツール
ユーザーがページ上でどこを閲覧・クリックしたかを可視化するツールです。代表的な無料ツールにMicrosoftのClarityがあります。ページ内のどの部分が注目されているか、逆に全く見られていない箇所はどこか、といった定性的な行動分析に役立ちます。フォームのどの項目で離脱が発生しているかなど、通常のアクセス解析では分からないインサイトを得られるのが強みです。
-
PageSpeed Insights
Google提供のページ速度計測ツール。URLを入力すると、そのページの読み込みパフォーマンスをスコア化し改善提案を示してくれます。特にモバイルでの速度が低い場合の指摘は重要です表示速度改善によるCV向上の効果測定にも使えます。
-
Googleトレンド
特定キーワードの検索ボリューム推移を確認できるツール。最大5つまでキーワードを比較できます。Webサイト改善では直接の分析ツールではありませんが、ユーザーニーズのトレンド把握に役立ちます。例えば自社商材に関連するキーワードがいつ盛り上がるかを把握し、ピークに向けてコンテンツを強化するといった施策に活用できます。
-
Googleマイビジネス(現:Googleビジネスプロフィール)
会社名や店舗名で検索した際に、検索結果画面に表示されるビジネス情報を管理するツール。住所・営業時間などを適切に掲載し、ユーザーに正しい情報を届けられます。ローカルビジネスの場合は特に重要で、サイトへの誘導や行動分析(プロフィール閲覧数や経路検索数など)も確認できます。
以上のツールはすべて無料で使えます。
それぞれ得意分野が異なるので、目的に応じて組み合わせて活用するとよいでしょう。例えば「GAで流入やコンバージョンを追いつつ、ヒートマップでページ内行動を分析し、PageSpeed Insightsで技術的改善点を洗い出す」といった具合です。
なお、さらに高度な分析が必要なら有料ツールの導入も検討できます。
SEO分析にはAhrefsやSEMRush、ヒートマップではContentsquare(旧Clicktale)やCrazy Egg、定性調査ではUserInsightやオプティマイリー(A/Bテストツール)など様々あります。月額費用と引き換えに強力な機能を備えていますが、自社サイトの規模や予算に応じて必要なものを選択しましょう。
その他の分析手法やアプローチ
ツールによる定量分析以外にも、サイト改善に有用なアプローチがあります。
-
ユーザーインタビュー・アンケート
実際のユーザーや見込み顧客にサイトの印象や使い勝手についてヒアリングする手法です。定量データでは掴みきれない「なぜそう感じたか」「本当は何を求めているのか」といった生の声が得られます。後述する成功事例でも、ユーザーインタビューによりコンセプトを再構築したケースが見られました。アンケートフォームをサイト内に設置しフィードバックを募ることも有効です。
-
ユーザビリティテスト
社内外のテストユーザーに実際にサイトを操作してもらい、課題を観察する方法です。テスターが迷ったポイントや戸惑った箇所は多くのユーザーにとっても改善点となりえます。録画ツールを使って操作を記録・分析すると具体的なUI改善案が得られます。
-
A/Bテスト・多変量テスト
改善施策の効果を検証するため、ユーザーの一部に新しいパターンのページを表示し、残りには現行ページを表示して成果を比較する手法です。例えばボタンの色違いでCVRがどれほど変わるか、といった検証ができます。A/Bテストツール(※Google Optimizeは2023年に提供終了しましたが、代替としてOptimizelyやVisual Website Optimizer等)を活用すればコーディング知識がなくても実施可能です。データに基づき最適案を選定できるため、重要な改善を本番適用する前にリスクを抑えて試行できます。
-
競合ベンチマーク
同業他社や競合サイトと自社サイトを比較分析することも改善に役立ちます。例えば競合サイトでうまくいっていそうな導線設計やデザインパターンがあればヒントを得られるでしょう。ただし先述のとおり単純な模倣は禁物です。あくまで自社向けに応用できないかという視点で研究します。
これらの方法を組み合わせ、定量データの「なぜ」を定性調査で裏付けることで、より確度の高い改善施策を導き出すことができます。サイト改善は分析7割・実装3割とも言われます。ツールと手法を駆使して現状を深く理解し、効果的な打ち手を考案していきましょう。
結果が違う本格SEO運用代行なら
フリースクエアにお任せください!
プロのSEO運用代行を低コストで実現!
まとめ

Webサイトの改善は、一朝一夕で劇的な変化を遂げる魔法のようなものではありません。しかし、ここまで述べてきたように目的を明確にし、正しい手順で課題を見極め、ユーザー本位の改善を地道に積み重ねていけば、必ず成果は向上していきます。過去の勘や経験に頼るだけではなく、最新のデータ分析とユーザー理解にもとづいて施策を実行することが成功への近道です。
幸い、Googleアナリティクスをはじめ優れたツールは多く存在し、誰でも無料で使える時代です。まずは現状を把握するところから着手し、本記事で紹介した改善ポイントや手法を一つひとつ試してみましょう。サイト改善は継続的なPDCAサイクルです。小さな改善の積み重ねがCVの向上といった成果につながっていきます。
自社サイトを通じて安定したリード獲得や売上増を実現するために、ぜひWebサイト改善に計画的かつ継続的に取り組んでみてください。今日の一歩が将来の大きな飛躍につながることでしょう。成功を祈っています!
WRITER

ライターMT
ライターMTの記事一覧複数メディアのSEO対策担当者を8年以上経験。SEO知識の他に、健康、脱毛、恋愛、コンプレックスなどのジャンルも得意。これまで500本以上のコンテンツ制作と上位表示実績を持つ。
キーワード選定からライティングまでを一貫して行うため検索意図を把握する能力が高い。
Webサイト改善で成果を出す方法や重要ポイントを徹底解説
この記事が気に入ったら
いいね!しよう