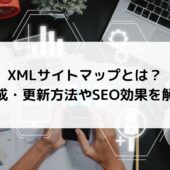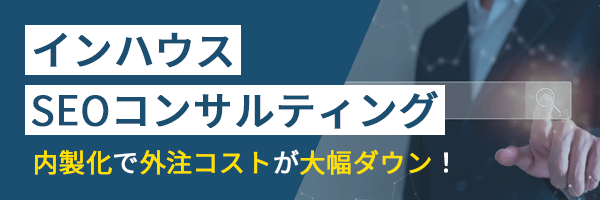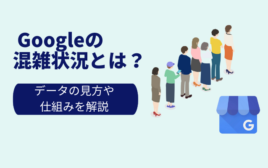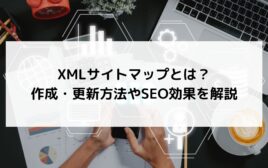- 2025.7.31
- SEO
ホワイトペーパーとは?作り方とダウンロード数増加のコツを徹底解説

BtoB企業のマーケティング担当者にとって、ホワイトペーパーは見込み客を獲得し育成するうえで欠かせないものです。本記事ではホワイトペーパーとは何か、どのようにマーケティングに活用すべきか、そしてダウンロード数を増やすには何が必要かを解説します。ぜひマーケティング戦略の参考にしてください。
結果が違う本格SEO運用代行なら
フリースクエアにお任せください!
プロのSEO運用代行を低コストで実現!
目次
ホワイトペーパーとは?

ホワイトペーパーとは、元々は政府や公的機関が発行する公式な報告書「白書」を指す言葉で、この意味が転じて、企業が提供する課題解決のための情報資料のことをホワイトペーパーと呼ばれるようになりました。
自社の商品・サービスに関連する領域の見込み客に役立つノウハウや業界データ、事例などをまとめ、PDFなどのダウンロード可能な状態で提供されます。多くの場合、Webサイト上で「お役立ち資料」や「○○ガイド」等で公開され、個人情報の入力と引き換えにダウンロードできるようになっています。
見込み客にとっては価値のある情報が得られ、その対価として発信側は連絡先などの情報を得られる仕組みで、企業と潜在顧客をつなぐデジタル資料としてホワイトペーパーは特にBtoBマーケティングなどで活用されています。
ホワイトペーパーの特徴と役割

-
潜在層へのアプローチ
大きな特徴は、企業視点ではなく顧客視点で構成されていることです。
単なる製品・サービスの宣伝ではなく、見込み客が抱える課題や悩みに対する解決策やヒントを提供することを主な目的としています。顕在的なニーズだけでなく、まだ課題が明確になっていない潜在層にも有効にアプローチできるのがホワイトペーパーの強みです。
例えば、BtoB商材では、導入までの検討期間が長くなる傾向があり、初期段階でいきなり製品の詳細や価格を提示されても顧客の関心を引くのは難しい場合があります。
そうした場面で役立つのがホワイトペーパーです。業界動向、課題の整理、事例紹介、解決策のフレームなど、導入前の情報収集段階で見込み客が求める内容を提供することで「この会社は自分たちの業界や課題を理解している」と思ってもらえる関係づくりができます。
-
リードの獲得
ホワイトペーパーはリードジェネレーション(見込み客情報の獲得)の有効な手段としても活用されます。企業のWebサイトや広告経由でホワイトペーパーのダウンロードを促すことで、見込み客から氏名、会社名、連絡先、役職などの基本情報を取得できます。
お問い合わせフォームのように「具体的な相談がある人」だけに限らず「情報収集中だが興味がある」という段階の潜在顧客にも接触できるため、より幅広く見込み顧客リストを構築できるのです。これは、MA(マーケティングオートメーション)ツールなどと連携させることで、効率的な見込み客管理やスコアリングにもつながります。
-
リードの育成
リードナーチャリング(見込み客の育成)にも非常に効果的です。ダウンロード後にステップメールやフォローコンテンツとして追加の情報を届けることで、見込み客は徐々に自社の価値や実績を理解していき、購買意欲を高めていきます。こうした継続的な情報提供により、自然な形で商談に移行する可能性が高まります。
-
商談支援
商談フェーズに入ってからもホワイトペーパーは有効です。営業担当者が業界動向や課題解決事例をまとめたホワイトペーパーを商談時に共有することで、企業の専門性や信頼性を強く印象づけることができます。見込み客が事前に自社の提案内容や価値について理解を深めているため、話がスムーズに進みやすく、最終的な受注確度の向上にも役立ちます。
このように、ホワイトペーパーは「潜在層へのアプローチ」「リードの獲得」「リードの育成」「商談支援」という一連のマーケティング・営業プロセスにおいて、極めて多機能かつ戦略的な役割を果たす存在です。単なる資料配布ではなく、顧客との関係構築を段階的かつ効果的に進めるための核となるコンテンツとして、積極的に活用する価値があります。
他の営業資料・白書との違い

マーケティングに使われるホワイトペーパーと混同されやすい資料として、営業資料(製品パンフレットや会社案内)や官公庁の白書があります。それぞれの違いを整理しましょう。
-
営業資料(サービス資料)
営業資料とは、自社の商品・サービスの仕様やメリットを企業側の視点でまとめた資料です。内容は製品カタログ、サービス紹介、導入メリットなどが中心です。ホワイトペーパーが顧客の課題解決に焦点を当てるのに対し、営業資料は自社商品の訴求に焦点を当てる点が大きな違いです。
-
公式な白書
政府や業界団体が発行する「白書(White Paper)」は、特定分野の現状や政策を報告・分析する公的な文書です。一般に販売もしくは無料公開され、広く情報提供することが目的です。マーケティング目的のホワイトペーパーはこれとは異なり、特定企業がリード獲得(見込み客情報の獲得)のために作成するマーケティング資料です。内容も自社の専門分野に関する情報提供が中心で形式は自由です(論文のような形式に限りません)。
ホワイトペーパーの種類

ホワイトペーパーには、内容や形式にいくつかの種類があります。自社の持つ情報資産や見込み客のニーズに合わせて、適切なホワイトペーパーのタイプを選ぶことが大切です。代表的なホワイトペーパーの種類とその特徴を紹介します。
ガイドブック型
ある分野の知識やノウハウを網羅的に解説する入門書的な資料です。制作工数は大きいものの、多くの潜在層にアプローチできダウンロード数が伸びやすいタイプです。
課題解決型(ノウハウ提供型)
特定のビジネス課題に焦点を当て、その解決方法を提示する資料です。「○○の課題と解決策」「△△を成功させるためのポイント」といったテーマが該当します。問題の原因分析から解決策の提案までを解説し、必要に応じて自社ソリューションの活用方法も盛り込みます。見込み客にすぐ役立つ実践的な内容となるためニーズが高く、ダウンロード後の検討促進にもつながりやすい形式です。
調査レポート型
自社もしくは第三者が行ったアンケート調査や市場調査の結果をまとめた資料です。業界トレンドやユーザー動向など客観データを示すことで、読者に新たな発見やベンチマーク情報を提供します。客観性が高く信頼されやすい反面、ホワイトペーパーの内容によっては競合企業や業界関係者からのダウンロードも多くなる傾向があります。また調査にはコストがかかる場合もありますが、得られたデータはプレスリリース配信等にも活用可能です。
事例紹介型
自社製品・サービスの導入事例や成功事例を複数まとめた資料です。他社の活用事例や効果を紹介することで、検討中の企業に具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。一般的に事例集はダウンロード率が高いコンテンツですが手間がかかります。
サービス資料型(製品カタログ型)
自社の提供するサービス概要や製品のスペック、価格表などをまとめた資料です。一見ホワイトペーパーとは異なりますが、Webサイト上で「○○サービス資料」としてダウンロード提供するケースが増えています。まだ営業資料をWeb公開していない企業は、まず最初のホワイトペーパーとしてサービス資料を用意するのも有効です。
テンプレート・チェックリスト型
読者がすぐ使えるフォーマットや自己診断シートなどのツールを提供する資料です。手軽に作成でき人気も高い傾向にあります。ただしダウンロードする人は具体的な課題を認識しているケースが多く、見込み客としてはすでに検討度が高い反面、母数は一般的なノウハウ資料ほど多くならないこともあります。
この他にも、セミナーやウェビナーの講演資料を再編集したものや、業界用語集・Q&A集などさまざまなバリエーションのホワイトペーパーが存在します。自社が持つ資産(知見、データ、顧客事例等)の中から見込み客に価値を提供できる情報を選び出し、適切な形式で編集することがポイントです。
ホワイトペーパーの作成手順

では、実際にホワイトペーパーを作成するにはどのような手順を踏めばよいでしょうか。基本的な作成プロセスを順に追って解説します。
目的の設定
まずホワイトペーパー作成の目的を明確にします。リードを幅広く集めたいのか、それとも今すぐ商談化しうる有望なリードを狙うのか、といった方向性です。例えば、認知拡大・裾野拡大が目的なら初心者向けガイド型を、商談創出が目的なら具体的課題解決型やサービス資料型を選ぶなど、目的によって企画の方向性が定まります。
ターゲットとペルソナの設定
次に、想定読者となるターゲット層を決めます。経営層向けなのか現場担当者向けなのかで求められる内容は変わります。自社の優先顧客層を念頭に、その典型となるペルソナ(人物像)を具体化しましょう。
テーマの選定
目的とターゲットに沿って、ホワイトペーパーのテーマを決めます。見込み客が抱える課題や関心事の中から、自社の専門性を活かして情報提供できるテーマを選びます。ここで、自社ブログ記事やセミナー資料など既存コンテンツも参考に、素材になりそうなものを洗い出すとよいでしょう。ホワイトペーパー1冊につき訴求するテーマは1つに絞るのが基本です。
構成(目次)の作成
テーマが決まったら、内容の大まかな構成(目次案)を作ります。ホワイトペーパーでは導入部で課題提起し、本文で詳細解説、最後に解決策提案というように、読み手が論理的に理解を深められるストーリーを設計します。例えば、課題解決型であれば「課題の背景・影響 → 原因の分析 → 解決策の提示 → 自社ソリューションの紹介」という流れが一例です。段落ごとの見出しをリストアップし、全体の流れを確認します。
原稿の執筆と編集
構成に沿って本文を書いていきます。最初は情報を詰め込みすぎず、伝えたいポイントをシンプルな言葉で書き出しましょう。専門用語はできるだけ平易な表現に言い換え、やむを得ず使う場合は補足説明を入れます。内容の正確性はもちろん、ターゲットが理解しやすいトーンか常に意識しながら執筆します。
デザイン・レイアウト
文章が完成したら、見やすいレイアウトを整えます。自社のブランディングに沿ったテンプレートがあれば活用し、なければフォントや配色、図表のスタイルを統一して読みやすい体裁に仕上げます。表紙やタイトルページには視認性の高いデザインを施し、ホワイトペーパー資料内で図解やグラフを用いて視覚的に理解を助ける工夫も効果的です。またページ数は内容と読者の関心度に応じて適切に調整し、冗長にならないよう心掛けます。
以上がホワイトペーパー作成の基本的な流れです。社内に蓄積されたナレッジやデータを十分に引き出し、読者にとって価値ある資料となるよう丁寧に作り上げましょう。
ホワイトペーパーの構成テンプレート

ホワイトペーパーの内容が決まったら、一般的な資料の構成要素に沿ってドキュメントを組み立てます。多くのホワイトペーパーで採用される基本的な構成要素は次のとおりです。
-
表紙
資料タイトルと副題、企業名やロゴを配置します。タイトルは内容を端的に表すとともに、読者の興味を引くキャッチーなものにしましょう(例:「○○担当者必見!今日から使える○○改善ガイド」など)。魅力的なタイトル・デザインの表紙はダウンロード率を左右する重要ポイントです。
-
概要(または目的)
このホワイトペーパー資料で何が得られるのか、読むと何が分かるのかを短い文章でまとめます。ホワイトペーパーの制作意図や読み手のメリットを冒頭で示すことで、ダウンロード後に「期待はずれだった」と思わせない効果があります。
-
目次
資料の目次を一覧で示します。ホワイトペーパーは10~30ページ程度のボリュームになることも多いため、最初に全体構成を提示して読み手に内容の全貌を把握してもらいます。
-
本文(解説パート)
メインコンテンツにあたる本文部分です。前述の構成案に沿って章立てし、図表やスクリーンショットを交えながら解説します。段落ごとに見出し(H2やH3見出し)を付けて読みやすく構造化することが大切です。読み手が途中で離脱しないよう、一貫したストーリーラインに沿って話題を展開しましょう。また必要に応じて適宜まとめの箇条書きやコラム枠を挿入し、ホワイトペーパーの中で重要ポイントを強調します。
-
会社概要
資料の巻末には、自社の基本情報を記載します。会社名、所在地、設立年、事業内容などを簡潔にまとめ、読者が安心できるようにします(特に初めて接点を持つ潜在顧客向け資料では信頼感につながります)。
-
問い合わせ先
最後に、資料を読んだ人が次のアクションを取りやすいよう連絡先を明示します。具体的には、自社の問い合わせ窓口(部署名、電話番号、メールアドレス等)やサービスサイトのURL、担当者名などを記載します。資料によっては執筆者のプロフィールや写真を載せ、専門家からの情報提供であることを示す例もあります。明確な導線を示すことで、興味を持った見込み客が商談に進みやすくなります。
上記は一例ですが、多くのホワイトペーパーに共通する基本パーツです。内容に応じて適宜章立てを増減したり、参考資料や用語集を付録として加える場合もあります。自社の目的や読者ニーズに沿って、マーケティングに役立つ最適な構成を検討しましょう。
ホワイトペーパーのダウンロード数を増やす施策

せっかくホワイトペーパーを作成しても、ダウンロード数が伸び悩むことはよくある課題です。ここでは、ホワイトペーパーのダウンロード数を増やすための工夫や施策を紹介します。
内容テーマの精査と魅力的なタイトル設定
まず前提として、提供するホワイトペーパー自体がターゲットの関心に合致していることが重要です。見込み客が本当に求めるテーマを扱いましょう。その上で、タイトルや表紙デザインを工夫して「この資料は役に立ちそうだ」と一目で思わせることが大切です。
資料内容の事前アピール
ホワイトペーパーの概要や目次、導入部分の一部などを公開し、ダウンロード前に内容がイメージできるようにしましょう。ランディングページやブログ記事内で「本資料で学べること」や図表のサンプルを紹介すると、ユーザーが安心して情報を入力できます。
「自社に役立つかもしれない」と感じてもらえるよう、ホワイトペーパーの価値を事前に伝えることがポイントです。
入力フォームの最適化(EFO)
ダウンロードに至るまでのフォーム入力が長すぎたり煩雑だったりすると、途中離脱の原因になります。フォーム項目は本当に必要な情報に絞り、入力しやすい設計にしましょう(例:郵便番号入力で住所自動補完、電話番号ハイフン自動挿入などのUX配慮)。また、プライバシーポリシーの明示や、入力いただいた情報の利用目的(例:「ダウンロード後に関連情報のメールをお送りする場合があります」等)の説明も忘れずに。フォーム最適化(EFO: Entry Form Optimization)を行い、ユーザーがストレスなく完了できる導線を整えることがダウンロード数増加に直結します。
関連コンテンツとのセット活用
ホワイトペーパー単独では存在に気付いてもらいにくいため、集客用コンテンツと組み合わせて露出を増やします。例えば、自社ブログでホワイトペーパーのテーマに関連する記事を公開し、その記事内で資料ダウンロードを呼びかけます(「詳しい手順は○○の無料資料で提供中!」等)。検索経由で記事を訪れた見込み客に対し、自然な形でホワイトペーパーをプロモーションできます。
実際、SEO記事とホワイトペーパーをセットで作成することで記事経由のダウンロード数が大幅に増えたという報告もあります。自社サイト内で高アクセスなページに適切なホワイトペーパーを配置する工夫をしましょう。
複数のホワイトペーパーを用意する
ターゲット別・テーマ別に複数のホワイトペーパーを用意すると、見込み客一人ひとりに響くコンテンツを提供できます。ダウンロードフォームに選択肢を設けるかたちで複数資料を提示しても良いでしょう。例えば、初心者向けガイドと上級者向けノウハウ集の2種類を揃えれば、幅広い層のユーザーを取りこぼさず興味に合った資料を提供できます。
コンテンツを充実させることでサイト全体の資料ダウンロード数アップにつながります。
コンテンツの質を惜しみなく提供
ホワイトペーパー内では有益な情報を出し惜しみしないことも重要です。ダウンロードしたのに内容が薄いと期待を裏切り、その後の信頼関係構築が難しくなります。「ここまで教えてくれるのか」と思わせる充実した内容であれば、読了後の満足度が上がり、他の資料もダウンロードしてもらえたり問い合わせへの前向き度も高まるでしょう。結果的に評価の高いホワイトペーパーは口コミで広まることも期待できます。
これらの施策を実践することで、ホワイトペーパーのダウンロード数向上に寄与します。ただし最も大切なのは、やはりターゲットにとって価値のあるホワイトペーパーのテーマを選び抜くことです。その上でマーケティングのプロモーションと導線を最適化し、多くの見込み客に届けましょう。
ホワイトペーパーの配布方法と導線設計

ホワイトペーパーを確実に見込み客に届け、効率よくダウンロードしてもらうには、配布チャネルの選定と導線(ユーザーの動線)設計が重要です。いくつか効果的な配布方法と導線設計のコツを解説します。
-
自社サイトでの配布
自社のオウンドメディアやコーポレートサイトにホワイトペーパーのダウンロードページを設置します。「資料ダウンロード」専用のページを用意し一覧掲載するほか、関連する各種ページ(サービス紹介ページ、ブログ記事、ニュース記事など)に適宜ダウンロード導線を配置します。サイト来訪者が興味を持ちそうな場所にCTA(Call To Action)ボタンやバナーを置き、自然に資料請求フォームへ誘導しましょう。
-
メールマーケティング
過去に獲得したリードや既存顧客に向けて、ホワイトペーパーのダウンロード案内をメール配信します。例えば、ニュースレターやキャンペーンメールで新規資料の公開を知らせることで、既存リードの再活性化にもつながります。ただし一方的な宣伝にならないよう、「課題解決に役立つ新資料を無料提供中」など有益性を強調した案内にすることがポイントです。
-
ソーシャルメディアでの告知
SNS(例えばビジネス向けの専門SNSなど)でホワイトペーパー公開の告知を行います。特にビジネス特化型のSNSはBtoB集客に有効です。投稿では資料のタイトルやサマリー、一部図表などを紹介して関心を惹き、ホワイトペーパーのダウンロードページへのリンクを掲載します。SNS広告を活用してターゲット層に絞り込んだプロモーションを実施するのも一手です。
-
Web広告・リターゲティング
ホワイトペーパーのランディングページへの集客を目的に、リスティング広告やディスプレイ広告を出稿する方法もあります。検索連動型広告で関連キーワード検索者にアプローチしたり、自社サイト訪問者へリターゲティング広告で資料ダウンロードを促すといった施策が考えられます。広告出稿は費用がかかりますが、特定のホワイトペーパーからの商談転換率が高い場合にはROIに見合う投資と言えます。
-
外部プラットフォームの活用
国内には企業向けのホワイトペーパーを集約した第三者運営のダウンロードサイトがあります(いわゆる資料ポータルサイト)。そうしたプラットフォームに自社ホワイトペーパーを掲載すれば、新たなリード獲得チャネルとなります。媒体によっては掲載に費用が発生しますが、自社サイト以外からリードを獲得する貴重な手段として検討する価値があります。
-
営業活動での活用
マーケティング部門だけでなく、営業部門もホワイトペーパーを活用できます。展示会やセミナーで名刺交換した相手にフォローメールでホワイトペーパーを含む資料を案内して、商談前後に「弊社でまとめた業界知見資料です」と提供することで、営業接点の強化につなげるホワイトペーパー活用は、営業現場でも効果的です。
配布にあたっては、見込み客が迷わずダウンロードできる導線設計が肝心です。
例えば、ランディングページでは入力フォームへの動線をシンプルにし、不要なリンクで離脱しないよう注意しましょう。ダウンロード完了後はサンクスページで次のアクション(関連資料の案内や問い合わせボタン提示など)を提示し、リードを逃さない工夫も重要です。マーケティングオートメーションツールを導入している場合は、ダウンロードトリガーの自動メール送信やスコアリング設定なども活用し、取得したリードを確実にナーチャリングしていきましょう。
ホワイトペーパー作成のよくある失敗と注意点

効果的なホワイトペーパーを作るには、避けるべき失敗パターンも把握しておく必要があります。ありがちなミスと、その対策となる注意点を押さえてマーケティングに活かしましょう。
-
専門用語ばかりで分かりにくい
自社の業界用語や略語を多用しすぎると、読み手に伝わらない恐れがあります。ホワイトペーパーは予備知識のない見込み客でも理解できる内容にすることが大前提です。専門用語は可能な限り噛み砕いた言葉に言い換え、必要な場合は注釈や用語解説を付けましょう。
-
商品・サービスの売り込み色が強すぎる
ホワイトペーパーは営業資料ではなく、あくまで顧客の課題解決のための資料です。自社ソリューションをあまりに前面に出しすぎると、読者は「結局宣伝か」と感じ離脱してしまいます。自社製品の紹介は最後の章に控えめに盛り込む程度に留め、まずは有益情報の提供に徹するのが信頼獲得への近道です。
-
ストーリー性がなく要点が散漫
資料全体を通して一貫した論理展開がないと、情報が点在して消化不良に陥ります。断片的なトピックの寄せ集めではなく、はじめに提示した課題が最終的に解決されるまでの筋道(起承転結)を意識して構成しましょう。章ごとに「何を伝えるパートか」を明確化し、全体のストーリーを損なわないよう注意します。
-
コンテンツが古く更新されていない
一度作ったホワイトペーパーも、時間の経過で情報が陳腐化することがあります。特に業界データや製品仕様、事例などは定期的な見直しが必要です。陳腐化した内容の資料を出し続けると信頼低下につながるため、定期的なアップデートや最新情報の追加を行い、常に鮮度の高いコンテンツを提供しましょう。
-
レイアウトが読みにくい
ホワイトペーパーの内容が良くても、文字ばかりで見づらい資料は最後まで読んでもらえません。適切に改行や段落分けを行い、図表や箇条書きを活用してビジュアルのメリハリをつけましょう。フォントサイズや色使いも統一し、誰が見ても読みやすいビジネス文書としての体裁を整えることが大事です。
以上の点に留意すれば、読み手にストレスを与えない質の高いホワイトペーパーに仕上がります。常に「読者目線」でコンテンツと表現をチェックし、初めて読む人でもスムーズに理解できるホワイトペーパーの資料作成を心掛けてください。
成果にコミットするSEOコンサルティングなら
フリースクエアにお任せください!
豊富な実績とインハウス(内製化)支援も可能!
まとめ

ホワイトペーパーの意味、種類、作成方法、ダウンロード数を増やす施策、配布・導線設計、そして作成時の注意点を解説しました。
ホワイトペーパーはBtoB企業のマーケティング活動において、見込み客に価値ある情報を提供しつつリードを獲得できる強力なツールです。
まだホワイトペーパーを活用していない企業は、小さな一歩でも構いませんのでぜひ取り組んでみてください。適切な施策を継続すれば、ホワイトペーパーはきっと御社のマーケティング活動の成果向上に寄与してくれるはずです。
WRITER

ライターMT
ライターMTの記事一覧複数メディアのSEO対策担当者を8年以上経験。SEO知識の他に、健康、脱毛、恋愛、コンプレックスなどのジャンルも得意。これまで500本以上のコンテンツ制作と上位表示実績を持つ。
キーワード選定からライティングまでを一貫して行うため検索意図を把握する能力が高い。
ホワイトペーパーとは?作り方とダウンロード数増加のコツを徹底解説
この記事が気に入ったら
いいね!しよう